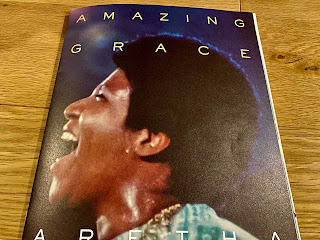元トーキング・ヘッズのフロントマン、デイヴィッド・バーンと、さまざまな国籍を持つ11人の仲間たちのステージをスパイク・リーが映画化した「アメリカン・ユートピア」をやっと観れた。
既に方々での評判を耳にして、かなり期待していたのだけれど、その期待をも超えて、打ちのめされるくらいに素晴らしかった。音楽、パフォーマンス、演出、照明、撮影、すべての面で画期的な音楽映画だった。
これでもかというくらいに表現の可能性を見せつけられて、自分ももっとやらなきゃという気持ちにさせられた。この余韻を大切にしたい。
現実を見据えた上での、とても開かれた人間賛歌であることにも深い感銘を受けた。絶望やシニシズムに安住しないバーンの柔らかな信念に強い共感を覚えた。
「Everybody's Coming to My House」を披露する前に、バーンは曲に関するエピソードを語り始める。
ハイスクールの合唱部がこの曲を歌った時に、バーン本人が意図していなかった包容力が伝わったことに感銘を受け、「そっちの方がいい!」と思ったのに、自分は今も自宅に人を招き入れるのが苦手だ。そんな内容だったと記憶している。客席の笑いを誘ったこの告白は、彼の人柄を伝える印象的なシーンだった。
バーンの語りやパフォーマンスは、状況への危機感を伴ったアンチテーゼや啓蒙的要素が強かったけれど、押し付けがましさを感じなかったのは、そこに「内省」が存在したからだと思う。完璧ではない一人の人間としての自覚が伝わるのだ。
正直に言うと、デイヴィッド・バーンに対しては、もっと頭でっかちなイメージを持っていたけれど、画面から伝わったのは、知的ではあるけれど、知性への懐疑も忘れない謙虚さだった。
彼のパフォーマンスは、知性と野生がとても高いレベルで手を取り合っていた。長いキャリアを経て実践と実感を積み重ねた成果なのだろう。実感を経た思想が肉体を通して体現されている様に、頼もしい説得力を感じた。
そして、ユーモアを忘れない姿勢。何よりもバーンは最上のエンターテイナー、芸人だった。こんな風に人を楽しませて、心のバランスや風通しをよくしてくれる力こそを知性と呼びたい。
映画撮影当時のデイヴィッド・バーンは67歳。とにかく心体のコンディションが素晴らしい。アンチエイジングとはベクトルの違う67歳ならではの若さ、瑞々しさを感じた。自身の変化を受け入れる勇気と柔軟性の賜物なのだろう。その姿勢は、バーンがこれまでの体験によって培った信念として画面から伝わった。
まずは自身に向きあい、自分を変えてゆく。あらがえない自身の変化を受け入れる。そうした一人一人の変化の自覚が、他者への寛容を生み、社会をよりよく変えてゆく希望の始まりとなる。自分がこの映画から受け取った大切なメッセージの一つだ。
何が本当で、何が正義がわからない時代においても、一人一人がこうした態度を積み重ねれば、世界はほんの少しずつましになってゆくんじゃないかと思う。
映画監督のスパイク・リーのこと、多国籍の11人の演奏者のこと、曲のこと、照明のこと、カメラワークのこと、語りたいことはもっとたくさん。受け取ったものが多過ぎて、まだ消化しきれない感じ。
とにかく、もう一度観に行こうと思う。
ー 2021年6月27日(日)